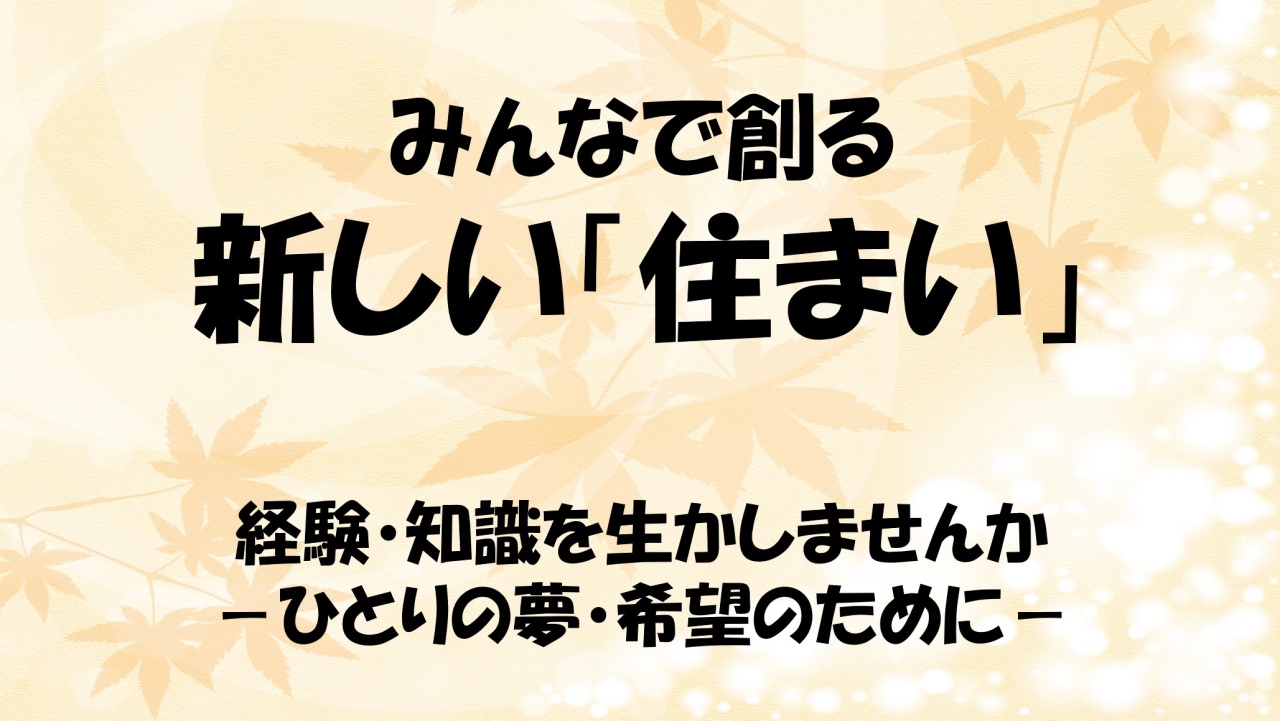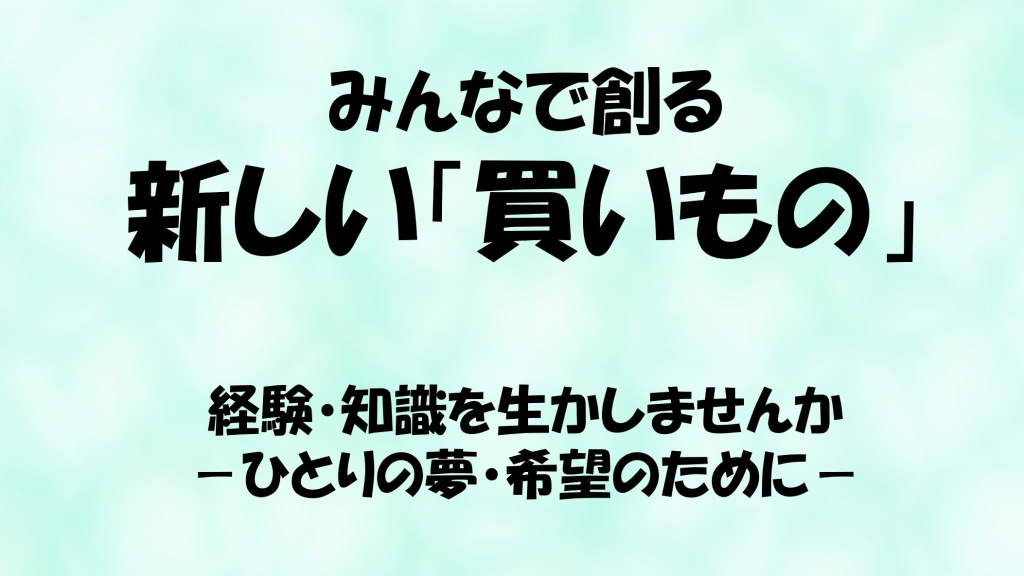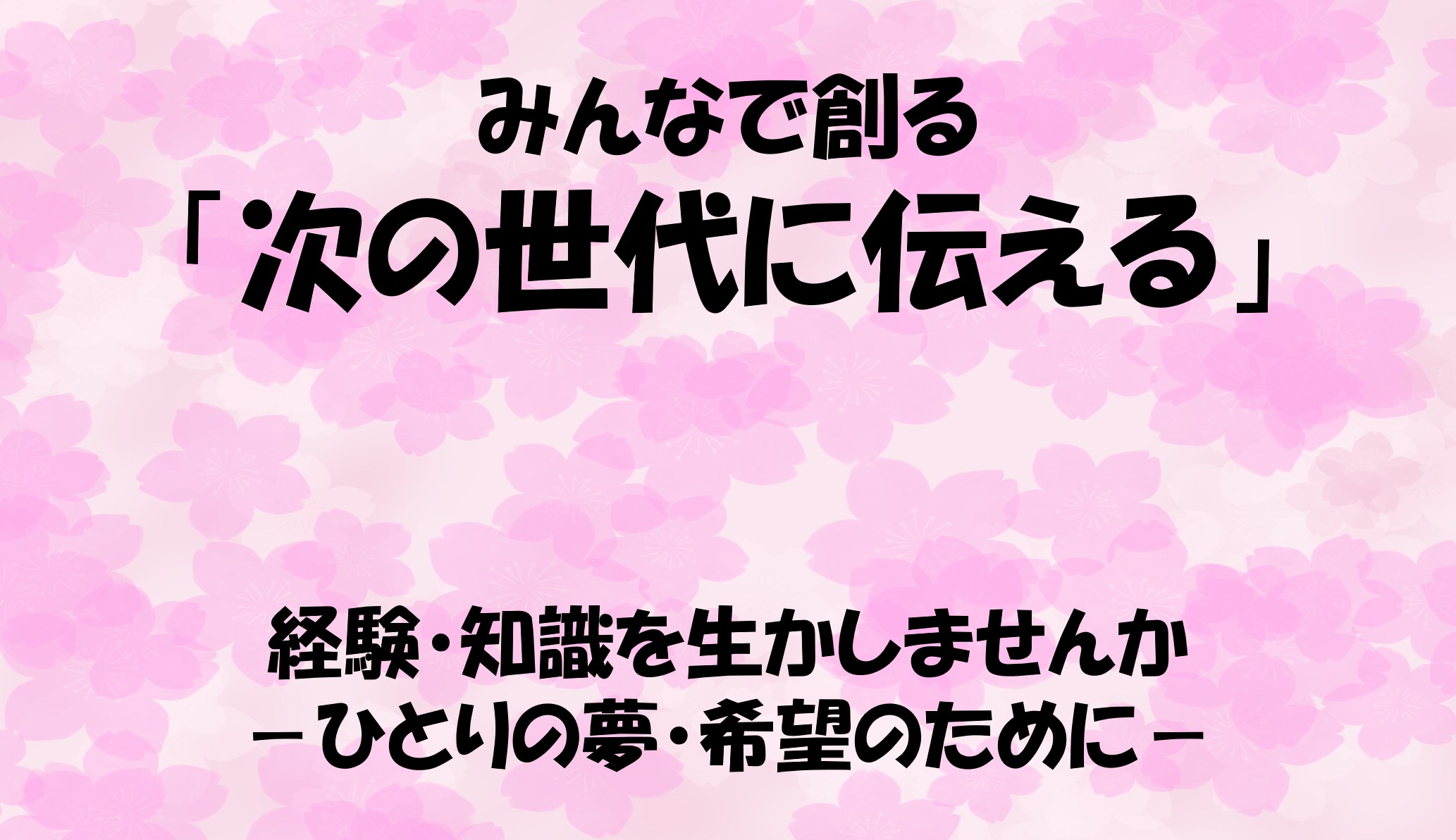~高齢OB世代と新しい社会を切り開く~
夢・希望とニーズ
私...
ひとりの夢・希望に向かってみんなが協力することで、一人ひとりが自身の夢・希望に向かって一歩踏み出すことができる社会を...
人が、自身の経験・知識を他の人の夢・希望実現に生かす!
経験・知識は社会の宝。経験・知識が眠っているのはもった...
生活の夢・希望が実現せず、残念な気持ちになることは良く経験します。
また、夢・希望に向かうとしても、さまざまな...
店・事業者の方々にとって顧客の確保・獲得は常に達成しなければならないテーマの一つ。
本サービスは顧客の確保・獲...
住まいを決めることは、間違いなく人生における大きな決断です。おかねもかかります。
問題は、私たち一般の消費者は住ま...
毎日の当たり前の、慣れ親しんだ風景:
買いもので店に入ると値引きやポイント付与の広告が目に入ります。
一見、...
次の世代に伝えるということばは知ってはいても行動されていない方が多いのではないでしょうか。
沢山の財産がある方は、...
何でもご意見下さい
内容や形式など何でも構いません、ご意見をいただければと思っています。
よろしくお願いいたしま...
関連記事